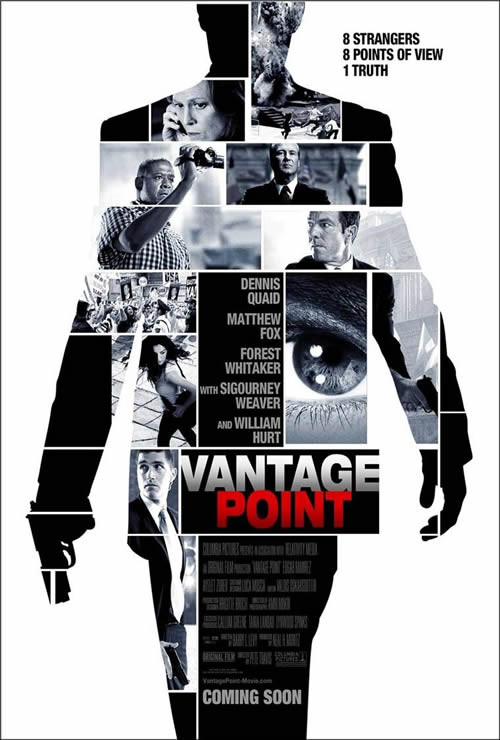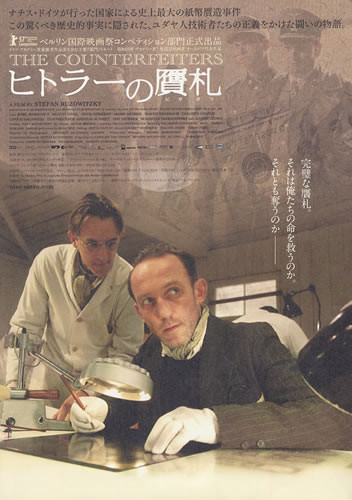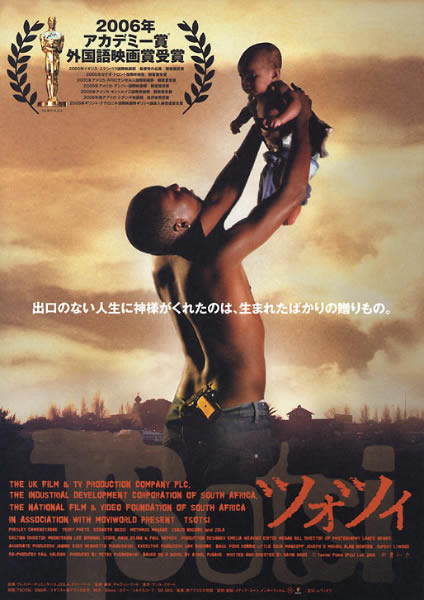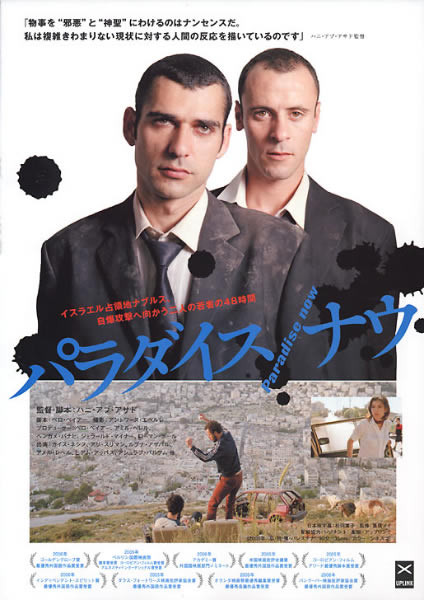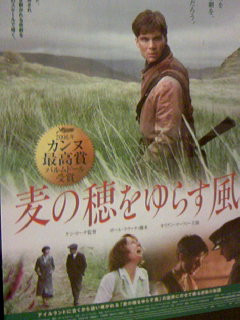「つぐない」
あちこちで高い評価を受けている作品でしたので、普段あまり触手の伸びない恋愛物語ですが見てきました。 大正解でした!
基本のプロットは、深く愛し合う若き男女のかなわぬ悲恋物語なのですが、本が良くできているので全体の構成がとても骨太、そして、演出も極上です。
第二次世界大戦前夜、舞台は夏の英国、物語好きの少女13歳のブライオニー(シアーシャ・ローナン)がたたくタイプライターのキー音に乗せた上品なBGとともに幕が開き、上流の暮らしぶりが披露されるかたちで、登場人物像などが描かれます。この冒頭は、お堅い文芸作品のニオイが強くて、ちょっと失敗だったかな?と思っていましたが、さにあらず、展開はどんどん深まっていきます。
大学を卒業したばかりの美しい姉セシーリア=スー(キーラ・ナイトレイ)と、使用人の息子で一緒に育ったロビー(ジェームズ・マカヴォイ) は、身分を超え惹かれあっています。若い二人が次第に近づいていく様を、幼い妹ブライオニーが垣間見ることで、多感な少女がほのかに恋心を抱いていたロビーへの複雑な思いからくる思いこみと嘘により、悲劇へとつながっていきます。
スーとロビーがぎこちなく、次第に深く近づいていく様子を、初めに妹の視線から描き、その後時間を戻し視点を変え、真実が描かれるという手法で、大人の世界と子供の価値観の差をうまく表現する演出が素晴らしいと思います。 二人のラヴシーンはエロチックですが非常に上品で、センスの良さを感じました。
妹の証言によって濡れ衣を着せられ、罪人となったロビーは牢から出る代償として兵士になり、戦争が勃発したフランス戦線に送られ、姉スーは家を出てロンドンで看護婦として働いています。 戦時中ロンドン、二人のつかの間の再会シーンも美しく涙を誘います。 そして、二人への仕打ちの罪の重さに気づいた妹も、看護学生となって、負傷した兵士のいる病院で手伝いをしながら、相変わらず物語を書いていますが、さらっと語られるこのシーンに、後への複線も張られています。
その後息をのむ映像が登場します。 敗走したイギリス軍が、ダンケルク海岸に集結し、「ダイナモ作戦」と名付けられた撤退を待つシーンですが、命からがらここにたどり着いたロビーと仲間2人が、丘の上から数十万人の人並みを見下ろし、「聖書みたいだ・・」とつぶやきますが、まさにスペクタクルな光景です。そこから数分間続く長回しの映像では、軍馬を射殺し、装甲車を破壊し、海を隔てた祖国に向きながら合唱する傷ついた兵士達など退却軍の現実が曇天のほの暗い色の映像で次々と描かれます。すごい! このあたりの映像作りが、単なる恋愛物語以上の深みを与えているのではと思います。
そして、驚きのエンディング。 タイトルとなっている「つぐない」の意味と、それまで描かれてきたストーリーの重みにあらためて気づかされることになります。 作家となった老齢のブライオニーが語る言葉から、前半の悲劇に至るまでの演出法や、つかの間の逢瀬を過ごす二人への描写の必然にも納得がいきます。
是非ご覧になり、深い感動と余韻を味わってください。若き才能ジョー・ライト監督の力量が光る、素晴らしい作品、オススメです。