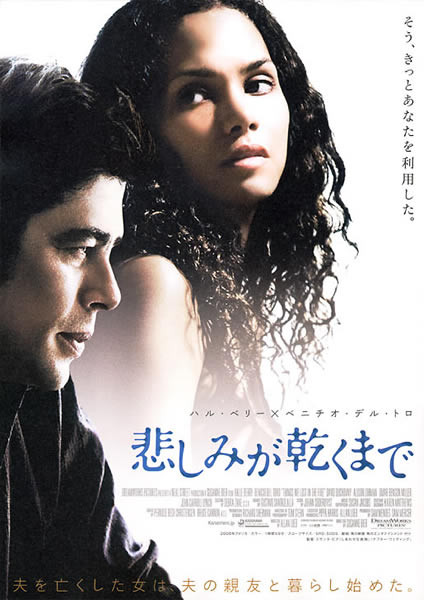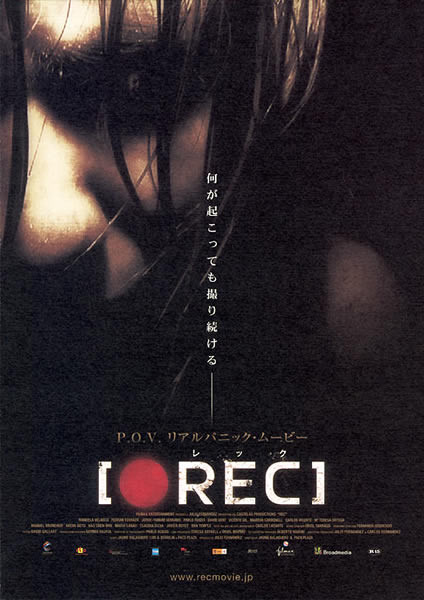迷子の警察音楽隊
 鮮やかな水色の制服を着た、浅黒く彫りの深い顔のアラブの男達が、所在なげに並んで迎えを待っている無言劇のような冒頭シーン(ポスターの絵柄も同じ)から、作品全体のトーンが伝わってきます。
鮮やかな水色の制服を着た、浅黒く彫りの深い顔のアラブの男達が、所在なげに並んで迎えを待っている無言劇のような冒頭シーン(ポスターの絵柄も同じ)から、作品全体のトーンが伝わってきます。
英国題The Band's Visit イスラエルの作品なのでヘブライ語の原題は読めません。
異国の見知らぬ土地に、図らずも滞在することになった警察音楽隊の面々、その一夜の出来事を綴った90分あまりの短い作品ですが、ほのぼのとした雰囲気とそこはかとないユーモア、絶妙の間がおいしい、いい作品だと思いました。
ア ラブの盟主エジプトの警察官たちが、隣国でありながら建国以来決して良好とは言えない関係にあるイスラエルに赴く。両国の関係、距離感などを深くは知らな くとも、その微妙なシチュエーションが、彼らの心細げな描写の根底にあることは容易に想像がつきますが、そのあたりについての深読みが必要とは思いません でした。
異国からの突然の来訪者と、それを受け入れる辺境の町の人々、それぞれが母国語でない言語でぎこちなくコミュニケーションをとり ながら、少しずつ心を通わせて行きますが、その過程の小さなエピソードの積み重ねによって登場人物像の輪郭も見えてきます。 このあたりの作りにも好感が持てます。
隊長と食堂の女主人との交流、若く女たらしの隊員が初な若者に恋の手ほどきをするシーン、枯れかけていた初老の隊員が希望を取り戻すシーンなど見所が何点かあります。それぞれが自然で、妙な教訓じみていないところもオススメです。
現代の大人の童話として、アラビアンナイトに書き足したいような作品です。