食料品消費税ゼロで物価は下がる?
一昨日、総理大臣が衆議院を解散する意向を会見で語り流れが決まったようです。与野党とも既に選挙モードです。野党では、ふたつの大きな政党が新党として合流するというエポックな動きもあり、多党化で、漂流気味だった日本の政治も、転換点にきたのかも知れないですね。
選挙に向け、各党が発信し始めています。詳しい公約は、議会の解散後に出てくると思いますが、成熟した日本では、もはやイデオロギー対立の色はほどんどなく、個別政策で違いを出そうとする方向になるのだと思います。当面、有権者の関心は、消費税、物価高に絡めた経済対策など、やはり生活に直結する問題のようなので、選挙に臨む政党はここらを中心に攻めてくると予想されます。
今の時点で、各政党が主張している、消費税に対するスタンスをまとめてみました。こういうとき力を発揮するのはAIですね。ChatGPTに、ここ数日ニュースで流れてくる政治ネタを指示して、解りやすい表にするよう頼んだら作ってくれました。全体に、ところどころ文字が変だったり、政党が発している実際とは微妙に違っているところもあるようですが、日本語のメリットで何となく意味は分かということで。
 令和8年衆議院選挙前、主な政党消費税に関するスタンス(ChatGPTによるまとめ)
令和8年衆議院選挙前、主な政党消費税に関するスタンス(ChatGPTによるまとめ)
恒久、時限問わず、食品に係る消費税は税率ゼロまたは現在より減税を唱えています。一昨年の衆院選の頃とは様変わりしています。何てことでしょう、これでは選挙の争点になりません。解散せずに、早く国会開いて審議してくれれば、早々に実現しそうですが、そうならないところが不思議なところです。政府は、国民のために一刻も早く消費減税を含む物価高対策を打ち出してくれるのではなく、政権の信任を問うのが優先と考えているのですね。(日本は代議制だから、国会で決めた総理大臣が正当で、あらためて選挙で国民に問う必要はないはずですが)
まあ、その辺の事情は永田町では大事なことなのでしょうから、庶民がとやかく申すのはやめておきます。今日書きたかったのは、食料品に係る消費税がゼロになった場合に出てくることで気づいた問題についてです。
長く食品の製造販売を営んできた経験から申すと、食料品が非課税(税率0)になった場合、小売販売者は、顧客から消費税を預かることができません。ところが、食品そのものの仕入れ(原材料)にかかる税がゼロになったとしても、販売(製造を含む)全般には、たくさんの経費がかかっています。
① 包装資材・消耗品 ② 水道光熱費 ③ 店舗関連費用 ④ 厨房設備・什器備品 ⑤ 外注費・サービス費 ⑥ 運送費・物流費 ⑦ 修繕・保守 など多岐に渡ります。これらは標準税率が課せられています。店頭に並べるまでの原価にかかった税について仕入税額控除ができなくなり、実質的にコスト増となります。当然、事業者は自己防衛せざると得ませんから、表示価格・中身を変えない形での「実質値上げ」とする可能性があります。消費者向けの商品やサービスの価格表示は「内税表示(総額表示)」が義務となっていますので、見かけの価格が課税されたか否かを判断するのは、よほど気を付けないと、消費者の目には判りにくいのではないでしょうか。(免税店といういう扱いだと異なるようです)
こうして、食料品の消費税ゼロは消費者には恩恵があるように見えますが、販売者にはデメリットとなります。あるいは、販売者が自己防衛のため現在の消費税分を所謂ステルス値上げするなら、恩恵は打ち消されてしまうでしょう。
各政党の皆さん、公約として受け入れられやすいかもしれないですが、分かりやすい政策ほど歪みを内包する。事業者行動を無視した制度設計の危うさを指摘したいと思います。結局消費者に恩恵が及ばないまま、税収減(予算の5%前後の縮減)だけが残ることになりはしないでしょうか。杞憂であればよいですが。
●手焼きせんべい風林堂のホームページ せんべい印刷「ぷりんたぶるせんべい」
●日々。おせんべいづくりについて書いている「手焼きせんべい処相模原風林堂のおせんべい日記」
●おせんべいに印刷「ぷりんたぶるせんべい」へのご注文お問い合わせ先
●趣味の風景写真を載せているブログ
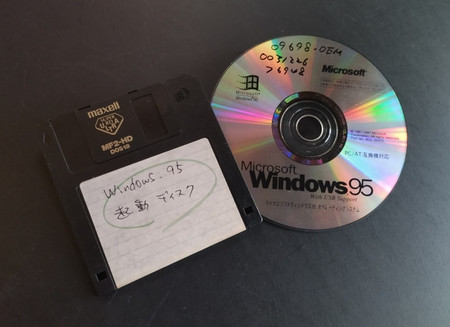



















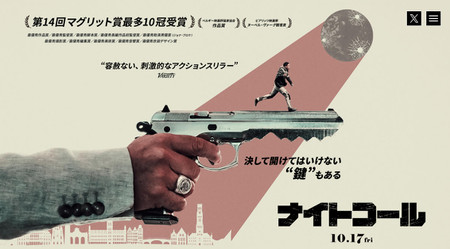
 熱気球の体験イベント
熱気球の体験イベント
 広い芝生広場にバラエティに富んだ沢山の出店者
広い芝生広場にバラエティに富んだ沢山の出店者

