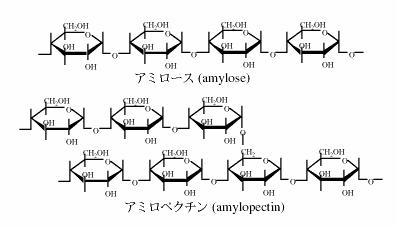おせんべい作り 仕込み編
強い台風9号が、静岡県~関東地方に接近する模様で、だんだん風雨が強まってきています。 恵みの水をもたらしてくれる台風ですが、雨風があまりに強いと、災害が心配され、農村部では、農作物への悪影響が、都市では、社会機能への厳しい結果に繋がりかねませんので、お手柔らかにお願いしたいものです。 既に交通機関には、色々影響も出ているようですので、明朝の通勤通学の足も心配されます。 私の息子の通う私立の中学校は、早々、明日午前中の授業を行わないことにしたようですが、電車通学の生徒のほうが多いので、そうせざるを得ないのでしょう。 台風退散 渇!!
今日は、風林堂の定休日でしたが、製造業でもあるおせんべいやは、製造の当日以前にも、準備が必要となりますので、休日の最後には、明日の仕事の仕込が待っています。 主なものは、おせんべい生地を焼ける状態にする作業ですが、つける醤油たれを補充するための仕込などもあります。 
今日は、生地の仕込みについて触れてみようと思います。生地作りの業者さんから送られてくるおせんべい生地は、そのままではおいしくは焼けません。焼く前に、そこそこの温度で加熱し、含まれている水分を取り除き、仕上がりの状態に合わせた按配にしてやる必要があります。 これを2次乾燥、「ほいろをとる」といいます。
金網の筒に入った生地。これから7~80℃で乾燥されます。↑
和菓子の工程でも、作るお菓子の種類によっては、オーブンの余熱を使ったり、専用の「むろ」といわれる道具などで、同じような作業をすると聞いたことがあります。おせんべいの場合には、主に熱源にガスを使った、「回転式ほいろ」という機械をつかい、この作業を行います。
上の写真のような、金網製の筒に、おせんべいの生地を入れ、数十分から数時間の間、ゆっくり時間をかけて暖めてゆきます。 この時間と温度の調整が、焼き上がりに大きく影響してきますので、神経を使うところです。 生地の仕上がり具合、厚さや大きさ、保存状態、時期なりの湿度や気温等等、影響を受ける要素はたくさんあります。 熟練とまではいいませんが、それなりの経験がものを言う作業なので、頭の中のHDDが錆付くと、困ったことになるかもしれませんね。 こうした下準備を終えて、初めて焼きの作業にかかれるわけです。 またの機会には、次の工程のお話を。