絶品「金胡麻せんべい」
おはようございます。 2月3月は、他の月より早く過ぎ去るとの故事の通り、桜の開花予想さえちらほら聞かれる時期になりました。 暖冬の今シーズン、菜種梅雨も早く訪れ、ここ2週間ずっとはっきりしない天候が続いていた相模原ですが、久しぶりの青空が見られそうになってきました。
 今日は久しぶりにおせんべい作りの話題です。 風林堂のサイトでもご紹介、販売している商品に、金胡麻入りの小粒煎餅があります。
今日は久しぶりにおせんべい作りの話題です。 風林堂のサイトでもご紹介、販売している商品に、金胡麻入りの小粒煎餅があります。
←焼き上がり味付けされた金胡麻せんべい。 いい香りです。
近年、若さを保つ栄養素として注目されている胡麻ですが、食材としてはかなり古いらしく、アフリカでは数千年前から、日本でも中国経由で渡来し、室町時代くらいから食用されたとされています。
古くは、漢方薬として使われた胡麻も、最近は料理素材としてのみならず、様々なお菓子に使われ、そのマルチぶりは、作り手としてもとても重宝するところです。
欧米では、白ゴマのみが重用されるようですが、日本では黒、白、そして金ごまがそれぞれ用途によって使い分けられています。 風林堂でも、黒ごま、金ごま2種類を使い、味付けもそれぞれ変えて何種類かの商品として提供させていただいています。
黒、白に比べ、金ゴマにあまりなじみの無い方もいらっしゃると思います。皮の色がキツネ色で、他の胡麻より少し小粒なのが特徴です。 そして、色のみならず、味と香りがまさに「金」なので、ゴマ好きの方には、堪えられない風味です。勿論お値段もそれなりですが・・。
生地を煎って火を通す間は、一面が香ばしい香りに包まれます。
一粒二粒お召し上がり頂ければ、その実力のほどがお解り頂けると思います。是非一度・・。

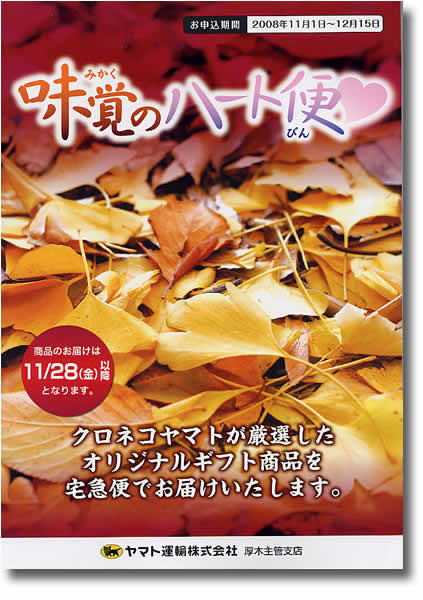







 手焼きせんべい
手焼きせんべい


 手焼きせんべい
手焼きせんべい






